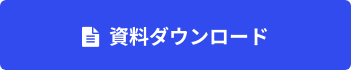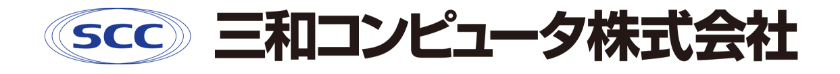2025年の崖とは?レガシーシステムへの対応策

2025年に企業が直面する「2025年の崖」とは、レガシーシステムに関連した深刻な問題を指します。レガシーシステムとは、過去の技術や仕組みで構築されているシステムのことを指し、1980年代に多くの企業が導入した、メインフレームやそれを小型化したオフコン(オフィスコンピューター)と呼ばれるコンピューターを使用したシステムなどが該当します。また、近年構築されたシステムでも「レガシーシステム化」している場合があります。サポートの終了が発表されていたり、既に終了している場合や、部分的な改修を繰り返した結果複雑化し特定の人しか利用できなくなっていたり、過去の技術や仕組みで構築されており、最新技術への対応が難しいものなどが該当します。経済産業省は、2025年までにレガシーシステムから脱却してDX(デジタルトランスフォーメーション)を実現しない場合、2025年以降で最大12兆円/年の経済損失が生じる可能性があると指摘しています。
長年にわたりビジネス運営の支柱であったレガシーシステムですが、その古い技術基盤は現代のニーズに合致せず、セキュリティリスクの増大、運用コストの高騰、イノベーションの妨げといった問題を引き起こしています。このガイドでは、レガシーシステムが抱える問題をどのように理解し、対応するかについて紹介します。
目次[非表示]
- 1.レガシーシステムの現状と未来の問題点
- 1.1.レガシーシステムの定義と特徴
- 1.2.レガシーシステムの重要性と存在理由
- 2.2025年に直面する主な問題点
- 2.1.運用コストの高騰・IT人材不足
- 2.2.技術的負債の蓄積とイノベーションの妨げ
- 3.2025年に向けた対応戦略と具体的な解決策
- 3.1.レガシーシステムの効率的なマネジメント
- 3.1.1.社内システムの整理と評価
- 3.1.2.段階的なアップグレード計画
- 3.2.レガシーシステムから最新技術への移行・リプレース
- 3.2.1.システム更新とクラウド化の推進
- 3.2.2.クラウド移行のメリットと選定時の注意点
- 3.3.人材育成と知識の継承
- 3.3.1.IT人材の育成方法
- 4.事前準備と進捗管理が重要
- 5.まとめ
- 6.三和コンピュータの取り組み
レガシーシステムの現状と未来の問題点
レガシーシステムは、1980年代から現在に至るまで企業や組織にとって重要な役割を担っています。しかしながら時流の変化に伴い2025年に向けた技術革新とビジネス環境の変化に対応できなくなってきており、その課題点が際立っています。特に、古い技術が新システムと互換性を持たず、セキュリティリスクが増大し、運用コストが高騰するなどの問題があります。
レガシーシステムの定義と特徴
レガシーシステムとは、新技術の登場により相対的に古くなってしまった技術や手法に基づいて構築されたコンピューターシステムを指し、現代のビジネスや技術要求に十分応えることが難しいとされます。新たな技術との比較で判断されるため「導入から何年経過したシステムをレガシーという」といった具体的な定義などはありません。レガシーシステムは、新しい技術との互換性がなく、保守や拡張が困難という課題があります。古いプログラミング言語やフレームワークで構築されているのが特徴で、新しいシステムやアプリケーションとの互換性が乏しく、データの統合・共有が難しい点が挙げられます。このような状況は、システムの更新やセキュリティ強化を困難にし、長年多数の独自カスタマイズが施された結果、新しい技術の導入や技術移行を複雑にしています。
レガシーシステムの重要性と存在理由
レガシーシステムは長年にわたりビジネスを支える基盤として、企業活動のさまざまな側面で重要な役割を果たしてきました。多くの場合、企業の核心的な業務プロセスや基幹システムを支えています。そうした背景から、レガシーシステムを簡単には置き換えることができず、更新や移行には大きなコストと時間がかかるケースが多くあります。
例えば、銀行の取引システムや公共機関が長年蓄積してきた顧客データベースなどのように、数十年の間に蓄積された顧客情報や取引履歴が含まれるレガシーシステムは、今日でもその運営において非常に重要な役割を担っています。これらのシステムは、その運用や管理に特化した技術や知識を要し、更新や移行を行うには膨大な工数と精緻な計画が必要とされます。
とはいえレガシーシステムの管理や移行は企業にとっては避けては通れない課題となっており、将来に向けた戦略的な取り組みが必須となっています。
2025年に直面する主な問題点
レガシーシステムはセキュリティの脅威に晒されやすい状態にあります。製造元のサポートが終了していることもあり、適切な保守やアップデートが難しいからです。また、古い技術やプログラミング言語、プラットフォームが利用されているため、最新のセキュリティ基準に準拠していない可能性がありサイバー攻撃のリスクが高まります。古いシステムを脆弱性のある状態で使い続けていたうえでのサイバー攻撃による損害は企業の信頼性や収益に直接的な悪影響を与えかねません。
運用コストの高騰・IT人材不足
2025年の崖は、レガシーシステムの運用コスト高騰とIT人材不足という問題点も抱えています。企業は古いシステムの維持・管理を行うために必要なリソースを確保する必要があり、運用コストも今後高額化していくことが想定され、IT予算の9割以上を占めることになるとも言われています。また、レガシーシステムの維持・管理を行える人材も年々少なくなっているため、特別なスキルを持つ人材を確保すること自体が難しくなってきています。
技術的負債の蓄積とイノベーションの妨げ
技術的負債とは、短期的な視点でシステム開発を行った結果、長期的に抱えることになった高い保守費や運用費を指します。技術的負債の蓄積がイノベーションの大きな障壁となり、新しいテクノロジーやサービスの導入が遅れれば遅れるほど、企業の競争力が削がれ、新製品の開発や市場の変動への迅速な対応が困難となり、市場での立ち位置を悪化させます。
技術的負債の解消に向けて、エンジニアやシステム利用者、経営層が密接に連携し、現行システムの機能やパフォーマンス、セキュリティ面での評価を行い、時代に合ったシステムへの移行計画を策定することが要求されます。
2025年に向けた対応戦略と具体的な解決策
レガシーシステムに依存する企業は、2025年の崖で多大な課題に直面します。この変革期において、早急な対応戦略立案と実行が求められます。
対応戦略として効率的なシステム管理、レガシーシステムから最新技術やクラウドへの移行推進、そして人材育成と知識の継承が重要となります。これらのアプローチにより、ビジネスの持続可能性と競争力を維持・向上させることが可能となり、セキュリティリスクの低減や運用コストの削減にも繋がります。
レガシーシステムの効率的なマネジメント
レガシーシステムの効率的なマネジメントは、絶えず変化するテクノロジーの世界で企業が直面する大きな課題です。時代に合わせ古いシステムを現代のビジネスニーズに合わせて運用し、効果的に改善する方法が求められています。そのためには、まず、自社で使用しているシステムを整理し、各システムの役割や重要性を理解することが重要です。
社内システムの整理と評価
まずは現存する各種システムの役割、性能、そして他システムとの依存関係を正確に把握することが重要です。これは、その後の更新や移行の優先順位を決定するための基盤となります。自社のシステムのリストアップを行い、それぞれのシステムがビジネスに与える影響度や更新緊急度を評価することで、限られた予算内で最も効果の高い更新プロジェクトにリソースを集中させることが可能になります。
段階的なアップグレード計画
レガシーシステムの段階的なアップグレードは非常に効果的な手法です。一度に全てのシステムを更新しようとすると、巨額の費用が必要になるだけではなく、更新作業中のシステム障害発生リスクも高まります。そのため、段階的にアップグレードを行うことで、各段階で発生する費用を分散させ、リスクを最小限に留めることが可能になります。また、計画を立て段階的に実施することにより確実性を高めることができます。
レガシーシステムから最新技術への移行・リプレース
古くなってしまったシステムはITインフラを最新の技術に更新することが不可欠です。最新技術への更新は、システムの性能向上、セキュリティの強化、保守の容易化を実現し、経営課題への対応やビジネスの競争力を高めることに直結します。たとえば、古いデータベースシステムを新しいシステムに移行することで、データ処理速度の向上やセキュリティ水準の高い環境を構築することができます。
リプレース、すなわち既存システムの全面的な置き換えに当たっては、事業の連続性を保ちながら、段階的かつ計画的にアップグレードを進めることが求められます。これには、事前の徹底的なインベントリ整理、リスクアセスメント、そして移行計画の策定が必要となります。新システムへリプレースすることはIT人材のスキルアップや知識継承にも寄与し、持続可能なシステム運用体制の構築に役立ちます。
システム更新とクラウド化の推進
近年、システム更新とクラウド化は企業の技術的課題を解決し、ビジネスの柔軟性と拡張性を向上させるために不可欠になっています。システム更新は、古いテクノロジーや非効率なプロセスを見直し、最新の技術に置き換えることを目的としています。クラウド化により、企業はリソースの管理や拡張をより柔軟に行うことが可能になります。
クラウド移行のメリットと選定時の注意点
クラウド移行は、コスト削減と柔軟性の向上という二つの大きなメリットを企業にもたらします。オンプレミスと比較して、クラウドサービスを利用すると、物理的なインフラの維持管理費用が不要になります。利用するリソースに応じた料金体系になっているため、企業の運用コストの削減に繋がります。さらに、クラウドサービスを利用することで、グローバルに分散したデータセンターのリソースを活用できるため、柔軟にスケールアップやダウンが可能となります。
しかし、クラウド移行にあたっては、事前の計画とセキュリティへの配慮が重要です。データの安全性を保ち、サービスの連携に問題が生じないよう注意する必要があります。自社が求めるセキュリティレベルやポリシーを確認し、クラウドサービスプロバイダーが提供するセキュリティ機能を組み合わせることが重要です。不正アクセスやデータ漏洩のリスクを最小限に抑えるためにも、クラウドサービスを選定する際は、クラウドサービス提供側のセキュリティ機能を確認しましょう。
人材育成と知識の継承
2025年の崖に立ち向かううえで、人材育成と知識継承は欠かせない課題です。人材育成は、レガシーシステムへの深い理解を育みつつも新しい技術を取得することが重要です。また、知識継承は、長年に渡り蓄積された専門知識や業務プロセスを次世代の担い手に確実に引き継ぐプロセスとなります。人材育成と知識継承をしっかり行うことにより、技術的な課題への対応能力を高め、将来にわたって企業の競争力とビジネスの持続可能性を保持することが望まれます。
IT人材の育成方法
テクノロジーの進化は日々加速しており、ビジネス環境も同様に変化しています。これらの変化に適応するために、従業員は最新のスキルと知識を常に習得し続けることが重要です。そのためには企業側が従業員に最新のテクノロジートレンドを学び続けるための支援も必要となります。また、実践的な経験を積むための環境整備も、実際の業務で活用するためには不可欠です。これにより、従業員は新たに習得した知識を実務に活かし、プロジェクトや業務改善に貢献できるようになります。このように、進化し続けるテクノロジーの波をうまく乗りこなすためには、企業におけるIT人材の育成とその継続的なサポートがカギとなります。
事前準備と進捗管理が重要
レガシーシステム更新は企業の成長に不可欠ですが、計画不足やリソース配分の誤りにより失敗するケースが散見されます。近年基幹システムの更新の過程で予期せぬ技術的問題が発生し製造ラインの停止を余儀なくされたり、サービス停止により顧客にも影響が及ぶ事例も報告されています。レガシーシステム更新プロジェクトを成功させるためには、プロジェクトの目標を明確に設定することが重要です。目標が不明確な状態では、プロジェクトチームの方向性がブレやすく、結果として時間と資源の無駄遣いになるリスクが高まります。また、プロジェクトの進捗に応じて定期的な見直しを行い、フィードバックを積極的に取り入れることも、プロジェクトの成功には不可欠です。
まとめ
レガシーシステムは、1980年代から現在に至るまで企業や組織にとって重要な役割を担っています。しかしながら時流の変化やテクノロジーの進化に伴い、徐々に現代の技術基準やビジネスの要求への適応が出来なくなってきています。2025年に向けた技術革新とビジネス環境の変化により、セキュリティリスクや人材不足などレガシーシステムの課題解決が急務となっています。
レガシーシステムは企業の重要な役割を担っているシステムに使用されていることも多く、更新やリプレースは容易に行えるものではありません。まずは自社が抱えているレガシーシステムの整理、段階的入替スケジュールの策定、クラウド移行の検討、IT人材の教育など計画的に推進していきましょう。
三和コンピュータの取り組み
メーカー保守切れ製品が壊れてからでは遅い!
潜む4つのリスク
最後に三和コンピュータの2025年の崖に向けた取り組みについて紹介します。三和コンピュータはメーカー保守が切れたサーバやストレージなどのIT機器を、第三者機関として保守を行う延長保守サービスを提供しております。
前任者からの引継ぎがうまくいっていなかったり、システムが複雑化しており移行計画に時間を要するケースも少なくありません。レガシーシステムに限らず社内の業務システムを搭載しているハード機器(サーバやストレージ)をメーカー保守が切れた状態で運用しているケースも見受けられます。
システム刷新までのつなぎの保守として延長保守をご検討してみてはいかがでしょうか。
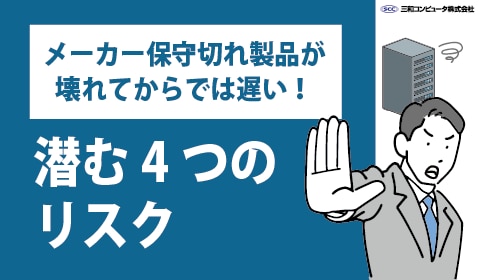
\3分で概要がわかる/